いつもトラクターのおもしろい話を教えてくれる、OPさんが興味深い比較をしてくれました。まとめきれるかわかりませんが、まとめてみます。
OPさんが使っている、DEUTZ(ドイツ)トラクターとマッセイファーガソントラクターの比較をしてくれています。言われてみれば、企業文化の違いなのでしょう、コンポーネントもほとんど変わらないトラクターなのに、細かいところでは色々と違うみたいです。その違いの積み重ねが個性になるのでしょうか? どちらも魅力的ではあります。

以下は引用です。
Deutz D4006(1968〜)
空冷KHD製3気筒ディーゼルエンジンで約40馬力です。インチアップにより車高が少しだけ上がっています。
利点はとにかく軽量!
重いフライホイールでもそこそこトルクがあり、軽快に走ります。
軽量ながらロングホイールベースで操作性や牽引力を確保しています。
アルミや高精度・高強度鋼材を使用しながら部品点数はおさえられています。欠点はパワーステアリングが無いこと、クラッチがやや重いこと、油圧揚力・油圧吐出量が少ない。三点リンクの負荷制御の調整が面倒。整備性やや悪い。特にブレーキはきついバネが使われていて整備にはかなりコツと力がいります。年式によって違いますが制動力もやや弱いです。
ロングホイールベースということは小回りはききにくいです。
MF135 前期(1965〜)
イギリス製 出力:45hp(グロス値)
エンジン:3気筒 AD3 152ディーゼルエンジン 排気量152.7立方インチ小型ながら当時としては小さな車体に見合わず高トルクで、個性的な排気音を響かせながら元気よく様々な作業をこなしました。その後当時としては画期的だった油圧シフト搭載やロングホイールベース化などのマイナーチェンジを受けながら、最近では数を減らしつつあるものの近所でも多数活躍している姿を見られます。
利点は、とにかく小型軽量で小回りが効き、低速高トルクエンジン搭載で2WDながら高い機動力を発揮。当時としては画期的な機械式三点リンク負荷調整「ファーガソンシステム」を搭載。
欠点は、純正の直流ダイナモ(うちはすぐACオルタネータに交換しました)ではバッテリー上がりが起きやすい。
走行クラッチがかかとの位置にあり慣れないと踏みづらい。
PTOクラッチはさらに深く踏み込まなければならずさらに踏みづらい。
パワステ無し&小回りに特化した?キャスター角の影響でハンドル操作はしっかりと行わないと危険。
引用終わり
ほぼ同年代で同クラスの両者、どんな違いがあるのでしょう?

OPさんによると、MFのミッション部は一般的なフランジで固定しているのに対し、ドイツはえぐりを入れた上で強度を保ちつつ最小限のボルトで固定していうそうです。

ホイールもOPさんによれば、MFが一般的なハブリング&8穴で固定しているのに対し、ドイツは材料の違いもあるのかもしれませんが、6本のボルトのテーパー部だけで芯出しとホイル固定・ホイルのしなり力でゆるみ止めをしています。


OPさん、こう言ってます。「どちらが良いということよりもメーカーが変われば、全く異なる思想で作られていて個性があっておもしろいです。」
確かに、そう聞いてみると、デザインの違い、色の違い以上に違って見えるような気がします。日本のメーカーもクボタとヤンマー、三菱、イセキと、色々ありますが、一つ一つは小さなことでも積み重なって形以上の違いになっているのでしょう。
道理で国産のトラクターはどのメーカーが良いの?・・・と近所の人に聞いても「う〜〜ん」と、答えが返ってこないわけです。たった一つの「これだ!」という理由がある・・・というわけではなかったのです。
作った人、使う人の色々な考えがあるからおもしろい
こうやってみて見ると、MFの方が、Deutzに比べ若干部品点数は多そうです。しかし、どちらの部品もよ〜く考えた上にこういう数で、こういう形で・・・と、理由があって決めたはずなので、どちらが良いと一概に言えないのはもちろんです。
品物というかシステムの故障というのは、各部品の故障率の合計なのでしょうから、単純に考えれば部品が少ないほど故障が少ないと思われます。(もちろん、部品が少なくても故障率のやたら大きい部品を使っていたらあんまり部品を減らした意味はないですけど・・・)
ボルトを8本から6本に減らすにしても、そのまま減らしたんじゃ手抜きで、強度不足になっちゃうでしょうから、ボルトを太くしたり、材質を変えたり、ネジのピッチを細かくしたり、強く固定できるように考えると、コストという面ではキツくなりそうです。そうなると安い部品をたくさん使って強度を出すという考え方も出てきますね。
用途が単純で、負荷がかかっていないので少ない部品でいける・・・というのもあるかもしれません。たとえば、単純な構造のエンジン(50ccのカブのエンジン)を100倍の大きさにしてトラクターに積んでも大した仕事はできそうもありません。カブはあの大きさだから単気筒で行けるのでしょう。
部品点数を減らすにしても、増やすにしても、それに関わってくるのが作る人の思想と言うか、考えで、そこが個性なのかもしれません。
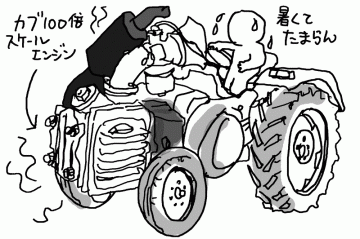
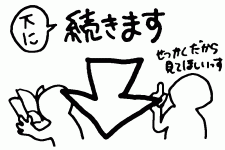
まだまだ写真と文章で長くなってしまうので畳んでおきます。続きを読むのリンクをクリックしてね!



Deutzはエンジンメーカー

よく出来たラジコンも
おまけに友達のMFのモデルも





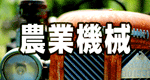
Dさん
その通りですよね
KTMとXR、主にKTMのほうの論文を書いてもらえたら
XRのほうを補足しますよ・・・ふふふ
違うから面白い、両方あるから面白いです
あ!
KTMはオーストリアのオートバイメーカー
XRはホンダのデザートバイクもしくはプレイバイクのブランドです
XRとKTMも違うよね。それと同じだよね。
野良通信さん
いつも興味深いコメントありがとうございます
プロが使って20年・・・これ以上に正解はないでしょう・・・きっと
値段にしたら数銭の木ネジでOKだったんですから設計の勝利です
でも、設計上正解でも、最近はユーザーに不安感や不快感を与えるような設計はNGだそうですよ
数銭が、必要以上の見栄えののための工作に数百円になって
それは当然ユーザーに転嫁されてしまうのでしょう
必要以上にお金を払いたくなければ
設計の能力も必要になってきそうです
一番最初に買った草刈機。 エンジンと刈り刃を繋ぐ軸を木ネジで止めてあった。プラスチック相手に木ネジで済ませることはそれで良いといえばそうなんだけれど「こんなんで?」と使って20年、最後は堤防を越えてきた高潮に水面下40センチに水没して、ピストンとシリンダが固着して御しまい。あの時すぐ分解して水洗いしていたら今でも現役だろう。
ちなみに、メーカーは国産、近くに工場があったので部品を何度か買いに行った。
今思えば、あれはあれで正解の設計だったのかなー。
最近の草刈機 でこんな止め方をしているのは見ない。