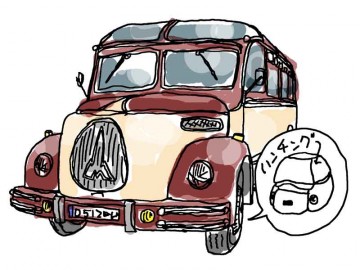
追加で色々と情報を仕入れて、なんだか本題から外れそうです。この車両、magirus deutz (マグリアス ドイツって読むのかなあ)で作ったバスで、ファイルの名前からすれば1951年製?!(ホントかよ)三面図まで見つけてしまいました。
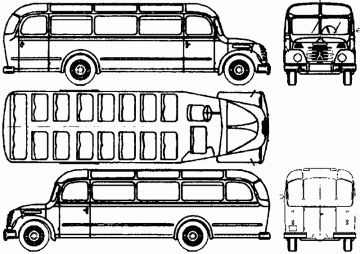
こちらも早速教えてもらいました

このパターンについて、OPさんに教えてもらいました。
写真のタイヤパターンは、アメリカの画像かと思います。
アメリカは地盤が固い畑が一般的なのか、比較的固めのバイアスタイヤが多く使われています。
何故あのパターンなのかはわかりませんが、アメリカのトラクタの画像は、ほとんどがそのタイヤをはいています。
なるほど!バイアスタイヤなんですね。一方、OPさんのところでは、雨も多く表面柔らかで、下はやや締まった畑が多いのでヨーロッパ製ラジアルが流行っているそうです。
ラグ面が固く、サイドウォールが柔らかなラジアルタイヤは、畑では高いグリップ力、舗装道路では片減りを押さえる働きをしてくれます。画像のうちのトラクタも後ろだけ履いてます。
と、おっしゃっています。クルマに履くバイアスとラジアルの違いと全く同じなんですね。
魅力的な形の数々




そして今

トラックに戻ってきてしまった


ホント、形がすばらしいです。昔、整備士をやったことのあるという、おじさんの話ですが、日本のいすゞが作っていた117クーペ、初期型は曲線のデザインで、ほぼ手作りだったそうです。ですから、きれいでカッコいいのですが、リフトで持ち上げると、こんにゃくみたいに前後が垂れ下がってきちゃうって言っていました。
そんな117クーペも後のほうになって、たくさん作るようになると、プレスラインが入ってしまってカッコが悪くなってしまったそうです。丈夫にはなったのでしょうが・・・・
似たような曲線を多用したデザインでありながら、このドイツトラックは丈夫そうに見えますね!



OPさん
おはようございます
確かにエンジンブロックとミッションケースが
フレームの役割を果たしていれば
部品点数が少なく抑えられそう
でもエンジンにバケットのマウントをつけたり
するのはエンジンに無理がかかるかも
どんなものにも良い部分と、少し困った部分
両方併せ持っているということですね
あ”~~っ!!新型のドイツアグロトロン欲しいです!!
補器類や制御関係は電子化されましたが、今でもほとんどのトラクタはエンジンブロックとミッションケースがフレームの役割を果たしてます。
ジョンディア等一部のメーカーはフレームにエンジンとミッションを搭載する格好になってます。コストはかかりますが、アタッチを装着する際にあらかじめ強度があるので簡単になるなどの利点があります。