今日は国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その番外編。特別展以外の通常展示で見たブログのテーマにぴったりの稲の展示です。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。
時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。
日本各地の大学・研究機関や企業などから、
600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!
科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、
“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。
中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、
「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!
もう終っちゃいましたけどね。
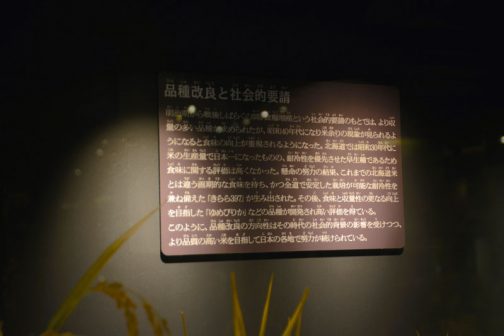
品種改良と社会的要請
明治期から戦後しばらくの間、食料増産という社会情勢のもとでは、より収量の多い品種が求められたか、昭和40年代になり米余りの現象が見られるようになると食味の向上が重視されるようになった。北海道では昭和30年代に米の生産量では日本一になったものの、寒冷性を優勢させた早生種であるため食味に関する評価は高くなかった。懸命の努力の結果、これまでの北海道米とは違う画期的な食味を持ち、かつ全道で安定した栽培が可能な耐冷性を兼ね備えた「きらら397」が生み出された。その後、食味と収穫性の更なる向上を目指した「ゆめぴりか」などの品種が開発され、高い評価を得ている。
このように、品種改良の方向性はその時代の社会的背景の影響を受けつつ、より品質の高い米を目指して日本の各地で努力が続けられている。

日本のイネに関しても、昔からの各地の気候にあったさまざまな品種が生み出され、栽培されてきた。そこには日本のバイオテクノロジーの原点を見ることができる。しかし現在では、かつてあった多くの品種は顧みられることなく、消費者に人気のある特定の銘柄だけが作付け面積を増やしている。多様性が減少しているのは自然界の話だけではない。先祖がつくった技術体系と品種の多様性を維持するために、私たちの努力が必要とされている。
とこのように書かれ、日本に存在してきた様々なイネの品種を培ってきた技術の産物である多様性と捉え、経済製だけを考えあるひとつに収束した結果、他のものが途絶えることの危機感を訴えています。確かに過去、このようなことが幾度となく起きてきましたものね。一度途絶えてしまったものは復活させることが難しいですから・・・
本州と北海道品種の比較
これは、本州の代表的な栽培品種である「コシヒカリ」と「ササニシキ」を、北海道の環境で育てたものである。右側に展示している北海道の代表的な品種「きらら397」と同時期に作付けを行い、「きらら」が収穫を迎えた時に刈取りを行った。この時点で、コシヒカリ、ササニシキとも収穫できる状態ではない。収穫時期まで待つと霜害にあう。このため、本来、熱帯性の植物であるイネを夏の短い寒冷地で育てるには、品種改良によって生育期間を短くする必要がある。
とあります。写真ではわかりにくいですが、「きらら」が黄色くもう収穫できるのに対し、「コシヒカリ」と「ササニシキ」はまだ青く未成熟な写真が示され、気候によって品種改良が必要であることが説かれています。多様性が失われた状態で「今」人気のある品種ばかりを作っていると、気候が変動したり、嗜好が変わったりした場合に対応ができなくなる・・・ということなのでしょうね。
すみませんっ!!!時間がなくなっちゃいました。この続きは明日ということで・・・


