
梅雨に入ったせいか、やたらカタツムリを見かけます。あっちをヌメヌメこっちをヌメヌメ・・・たまたま窓ガラスにくっついていたカタツムリを見ていてビックリ 口があるんですねえ(あたりまえなんですけど)。しかもその口、サメのようなエイのような、なんだか「カタツムリにはこんな口が付いていて欲しい!」ってのと全然違う感じなんです。
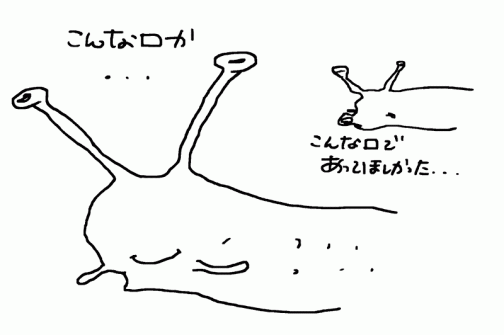
口が下面に付いている生き物ってみんなこんな感じなんですかね? こそげとるような、前に引っかかるような、若干攻撃の意図が感じられるような口です。

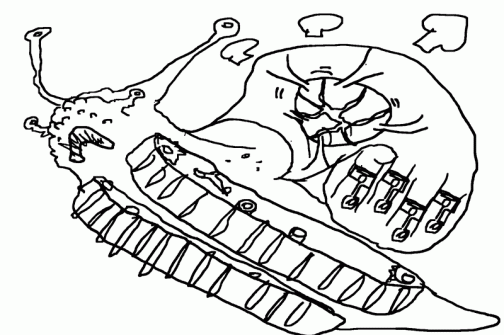
おなじみの生き物であるためか、ウィキペディアの記述もボリュームがあります。
全てのカタツムリは軟体部が湿った状態でなければ生きていけない。また暑さ寒さによっても活動に支障が出る。このような時にはカタツムリは物陰に潜み、殻の中に軟体を引っ込めて、殻口に粘液の膜を張る。この膜は専門用語で「エピフラム」(epiphragm)と呼ばれるもので、乾燥するとセロファンや障子紙のような質感の膜になり、軟体を乾燥から守る。またエピフラムには微小な穴も開いていて、窒息しないようになっている。
触角のある頭部下面には口があり、口内の上には顎板(がくばん:jaw)が、底部にはおろし金状の歯舌(しぜつ:radula)があり、後者で餌を磨り取って食べる。ガラス面を這うカタツムリの口を観察すると赤味を帯びた小さいものが見え隠れすることがあるが、これが顎板で、さらによく見ると顎板の動きと呼応して透明の歯舌の運動も見られる。口は食道から胃へとつながり、奥の方でUターンして殻口近くで肛門となる。
なるほど・・・カタツムリヌメヌメダイヤフラムか・・・下に転がっているカタツムリや、ブロック塀に貼付いているカタツムリ、死んでいるわけではないのですね。口に戸をたてて乾燥から身を守っていたのですか。それにしても上から太陽に照りつけられて煮えてしまわないんですかね?
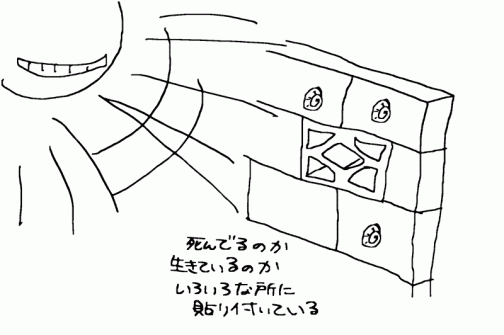





kobassanさん こんばんは
僕にはオサムシの仲間の中で『マイマイカブリ』は区別付きませんが
それらしきものは見かけます
カタツムリとマイマイカブリが両方見つかった時にやってみます
マイマイカブリですからかぶりつくんでしょうね・・・きっと
こんばんはnoraさん かたつむり つながりの話です。
誰もが知る手塚 治虫氏、彼が甲虫のオサムシが好きでこの名ができたと言われていますが、なかでも日本固有の『マイマイカブリ』が好きだったそうです。地味ですが、かたつむりがいる所に必ずいる虫ですから見てください。進行方向に、かたつむりを置くと面白いです。