もう7年
たまに思い出したように環境保全会の活動報告をするわけですが、それでちょっと勘定してみると『水戸市大場町・島地区農地・水・環境保全会便り』は2010年の3月から始めたので、なんともう7年になります!!!
広報
多面的機能支払交付金活動の中には必ずしもやらなくていいみたいですが「広報」という活動の項目があります。
地域の人みんなの財産である農村の自然とか農業環境を保全する活動をするだけでなく、活動していない人にも知らせよう!・・・というわけです。
『伝える』ってどういうこと?
「広報」といえば広く報じることで、つまりそれは『伝える』ってことだよね?『伝える』って知っているようで知らないし、どういうことか実験してみよう・・・という気持で始めたように記憶しています。
無人島で愛を叫ぶ
インターネットを使うのは「お金がかからないから」という理由からでした。
すぐにわかったのは「伝える」は「伝わる」とセットなんだ!ということです。
初めは検索エンジンに拾ってもらわない限りネットの世界では存在していないようなものですから、誰も見にこないわけです。
当たり前ですが、誰もいないところで大声で叫んでも気がつく人はいません。これでは伝えたことになりませんよね?
わかってる人は見ない。わからない人も見ない。
でも、しばらくして検索エンジンに拾われ、ようやくネットの世界の人になったとしても状況は大してかわりませんでした。
それはなぜか・・・見たい人がいないからです。
見るとしたら、活動を既にやっていて、他のところではどうしているか知りたくなった人くらい。活動の存在をを知らない人は、当然知りたいと思いようがないので見にきません。
つまりその活動を知っている極少ない人しか見にこないんです。これって「広報」じゃないですよねえ・・・
そこで「コマセを撒いて魚を釣る」作戦
そこで多面的機能支払交付金活動の枠を「農業」というくくりで考え、その中の「農業機械」というもので人を呼べるんじゃないか?と、仮説を立てて実行してみました。「コマセを撒いて魚を釣る」みたいな感じです。
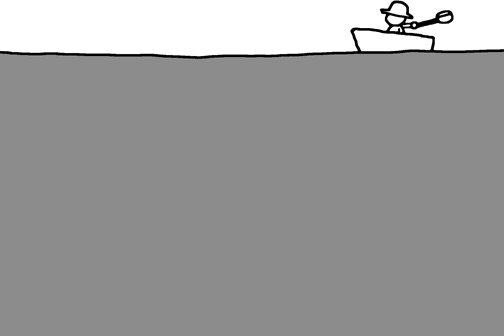
でも、この「コマセを撒いて魚を釣る」作戦はうまくいきませんでした。だって、見に来る人は大抵目的を持ってきていますから、コマセを撒いて魚が集められたとしても、それ以外のものに食い付いてくれません。食い付かせるためにはさらにもう一段階必要だったんです。
必要なのは「習慣化」
これは今のところの結論なのですが、ネットを使って雑誌や新聞のような「目的外のものがたまたま目に入った」ってことを作り出すためには、「習慣化」という物が必要ってことじゃないでしょうか?
わかってきたことを初めからつなげてみると・・・
毎日「農業機械」の記事を書く(これは僕の習慣化ですね)
↓
見た人の中で毎日見る人が出てくる(その人にとっての習慣化)
↓
たくさんの「農業機械」の記事の中に混ぜられた多面的機能支払交付金活動の記事をうっかり読んでしまう人が現れる。
こんな3段論法です。
で、収支を見てみると・・・
7年ほどの間に2267件の(そのうち1287件が「農業機械」の記事)コマセ記事を書き、そこへ287件のエサを(多面的機能支払交付金活動の記事)を混ぜた・・・ということになります。
「広報」とは
・・・
「広報」広く報じる、知らせるって膨大なコマセが必要ってってことなんですねえ・・・
エビで鯛を釣ろうとしているわけですけど、そのコマセのエビの量はハンパじゃない感じです。収支的に言ったら鯛でエビを釣るようなものかもしれませんね。
好きなことの片手間に必要なことを伝える。そんな状態になっちゃっているけれど、それぐらいで丁度。イヤイヤやったら絶対に伝わらない。
そんなところでしょうか。
いや〜〜〜〜『伝える』って難しいなー。

